人事系・労務系の人気資格である社労士(社会保険労務士)。出題科目が多く、実務型試験であるため細かい知識が問われます。
もっとも平成27年度本試験の合格率は過去最低になったように、今後は難化傾向も想定したいところ。特定社労士の誕生など、新たな業務拡大への新ステージに進むからです。
参考 2015社労士試験合格発表、合格率2.6%の衝撃、来年は? | 速報試験ニュース
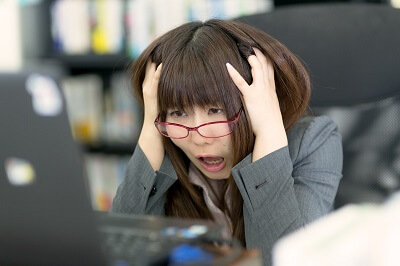
(画像はイメージです。)
そんな社労士試験対策の学習ですが、「出題範囲の広さ」「各科目において細かい知識が問われる」からと言って、最初から全科目を細かく取り組むのは賢明ではない。覚える知識が多いからこそ、最初の段階で全体像を把握しておくことが大切です。これは初学者の方に特に当てはまります。
社労士試験の出題範囲の全体像をつかむために、入門テキストも発売。中心部分を分かりやすく説明されているのが特長です。そして更に分かりやすさに特化したのが「学習マンガ」です。喜怒哀楽ある主人公を中心にストーリーが進むため、楽しみながら読み進めることができます。
そんな社労士試験向けの入門マンガについて2大書籍を比較します。
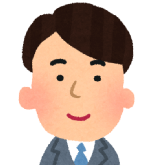
漫画で学習とはけしからん!
そんな声も聞こえてきそうですが、入門段階で漫画で効率よく学習を進めることは、きわめて合理的な学習法です。
現に社労士試験のほか、宅建試験、行政書士試験、司法書士試験向けの学習漫画も発売されており、好評を博しています。
社労士漫画(入門レベル)の比較
マンガでわかるはじめての社労士試験
宅建試験や行政書士試験などの法律系資格、社会福祉士や介護福祉士など福祉系などのテキスト・問題集を数多く制作・発行するコンデックス情報研究所による社労士試験向け学習漫画「マンガでわかるはじめての社労士試験」です。
漫画とイラストをふんだんに使い、法律知識ゼロの初学者の方を想定して分かりやすさを追求。社労士試験では理解に加えて暗記も最終的には必要ですが、そのような学習法も掲載しているのが特長です。
- 漫画だけでなく、図解が多い。理解がダブルで進む。
- 要点がパッとわかる。細かい記憶まで要求される社労士試験の勉強で、はじめの一歩に最適。
- 法律用語の解説など、まったくの初心者でも安心。
- 暗記や学習のコツ、社労士試験の攻略法も掲載。よきコーチに。
また著者の大槻哲也先生は現役の社労士であり、労働に関する各種専門委員も歴任。また明治大学大学院経営学研究科での講師経験もあり、本書も安心して読み進めることができます。
マンガはじめて社労士
本格的に試験対策の学習に取り組む受験生の方に最初におすすめしたいのが、兒玉美穂先生の「マンガはじめて社労士」です。入門レベルの内容をマンガで描いてあるので、無理なく概要をつかめます。
また原作者である兒玉美穂先生は特定社会保険労務士として実務に取り組む一方、大学で講師として活躍するなど指導経験も豊富です。そんな兒玉美穂先生の分かりやすさが特長です。
この書籍のデメリットとしてはメイン科目のみの掲載となっている点です。社労士試験では「一般常識」が出題され合否の分かれ目となることが少なくありませんが、本書ではフォーローされていません。
もっとも兒玉美穂先生による同シリーズ「マンガはじめて社労士 一般常識」が発売されています。したがって一般知識対策の基礎固めはこちらを利用されると良いでしょう。

この「マンガはじめて社労士」ですが、兒玉美穂先生の全体像を見渡せる今回のマンガのほか、「マンガでわかる資格試験シリーズ」として、「雇用保険法」「厚生年金保険法」「健康保険法」など、各科目が用意されています。
社労士試験の出題科目はどれも細かい知識・数字が問われますが、その基礎固めに活用されると良いでしょう。もちろん弱点分野(科目)の克服に利用する方法もおすすめです。
【まとめ】最新版が出ている「マンガでわかるはじめての社労士試験」で決まり。
ここまで社労士試験の学習漫画について比較・紹介してきました。どちらの書籍も販売実績があり、受験生の方におすすめが、最新の情報が重視される社労士試験ならば、2024年度版が出ている「マンガでわかるはじめての社労士試験」一択です。
もちろん各種テキストや問題集もそうですが、受験生の方それぞれに合った学習漫画もあるでしょう。ぜひご自分に合った学習漫画を比較・検討して利用してください。何度も繰り返し読むことで、スムーズに今後の学習段階に移行できるのではないでしょうか。
なお入門レベルの書籍として、今回の学習漫画のほか、テキスト中心の書籍もあります。多くの出版社が発行しており、学習漫画よりも少し情報量が多い。こちらについては別記事で扱います。
会社で起きている事の7割は法律違反
学習初期に効果的な書籍として「漫画」を紹介しましたが、合格後に社労士として活躍する姿をイメージすることも効果的です。それには実務に関する書籍を読むこともおすすめです。そんな書籍を紹介します。
それは朝日新書の「会社で起きている事の7割は法律違反」です。これは朝日新聞夕刊の連載「働く人の法律相談」の約4年半分から抜粋し、加筆・再編集したものです。
法令順守とよく言われますが、実際には違反をしているケースが多く、また雇用主も違反に気付いていないことも多いでしょう。
そこで本書では、全国のサラリーマンが持つ職場の悩みについて弁護士が回答しています。扱う内容も「パワハラ・セクハラ」「職場環境」「休暇」「有期雇用・派遣」「リストラ・解雇」「賃金」「労働組合」など多岐に亘ります。
社労士試験に内容に必ずしも直結するものではありませんが、「就業規則」や「労働協約」など試験対策で学習したキーワードも多数登場し、専門用語の理解度アップに役立ちます。

(画像はイメージです。)
何より実際にありがちなトラブル・悩みについて解決する事例形式になっているので、社労受験生の方ならば楽しみながら読み進めることができるでしょう。特に社会人の方には教養としてもおすすめです。
「今学習している内容がこんな風に役立つのか!」など、社労士試験対策の学習も興味を持って取り組めます。
いかがでしたでしょうか。他にも社労士業務のひとつである労働法に関する書籍は数多くありますが、「読みやすい新書」「イメージがわく具体的な事例が掲載されている」の2点から「会社で起きている事の7割は法律違反」を選びました。
今後社労士試験の学習を進めていくと覚える事項が多いため、煮詰まるケースも出てくるでしょう。そんな場合には最初にご紹介した学習漫画の復習や、実際のケースを扱った書籍(新書など)を読んでみることがおすすめです。社労士業務にも興味が出てきて、モチベーションのアップも期待できると思います。





